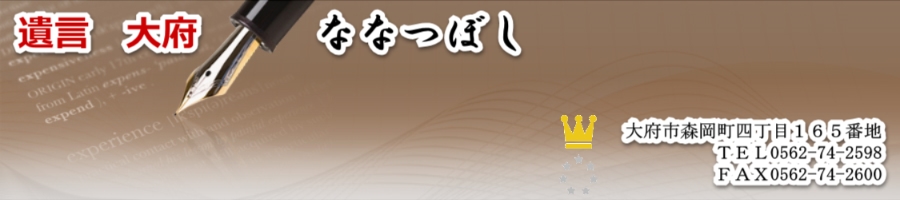
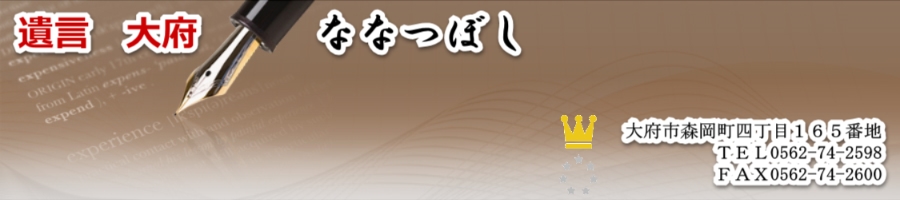
業務案内
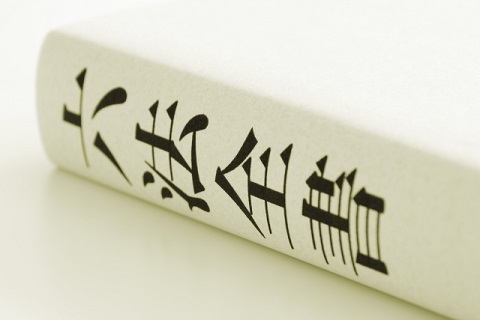
公正証書遺言 起案
証人手配
公正証書遺言とは公証人が作成に関与する遺言で、公証人とは裁判官などを退官された法律の専門家です。
公正証書遺言の利点は家庭裁判所での検認手続きが不要で、遺される家族に負担をかけることがないこと。原本が公証役場で保管されるので偽造、変造、紛失といった恐れがありません。
ななつぼしでは依頼者の方から誰に、どのような財産を、どのように与えたいのかを丁寧にお聞きし、遺言書の起案を致します。遺言の内容に十分にご納得いただけたら公証人との打ち合わせを代行いたします。
公正証書遺言には遺言者に人違いがなく、正常な精神状態のもとで自分の意思に基づいて遺言書が作成されたことを確認するために証人2人の立ち会いが必要となりますが、以下の方は証人となることが出来ません。
1 未成年者
2 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
つまり第三者的な立場にある人でなければ遺言証人になることが出来ないのです。とは言え、このようなことは例え仲の良い友人であっても頼みづらいものですし、遺言の内容が他に漏れてしまう心配もあります。ななつぼしでは職業上守秘義務のある証人手配を致します。
自筆証書遺言 添削
起案
自筆証書遺言は遺言の全文、日付、氏名を自分で書いた上で押印します。訂正をする場合にはその場所を指示し、どのように訂正したかを付記して署名し、かつ訂正場所に押印しなければなりません。
このように自筆証書遺言は法律的に間違いのない文章を作成することは困難なことです。方式や内容に不備がある場合にはせっかく作成した遺言が無効となってしまいます。
ななつぼしでは作成済みの自筆証書遺言に不備がないかのチェックをいたしております。
相続人の調査
現時点で相続人となる可能性が第1順位の人を推定相続人と言います。遺言者が推定相続人に相続させると記した場合は相続ですが、第2順位の相続人に相続させると記した場合には相続ではなく遺贈になる可能性が高いです。このような場合には真正な相続人から遺留分減殺請求を受けることがあります。他にも特に遺言者が高齢の場合には認知や養子縁組によって、遺言者が把握している推定相続人と異なっている可能性もあります。
また実際に相続が開始してから相続人の調査を始めると日本全国の自治体から戸籍を収集しなければならず、時間と手間がかかり相続人に多大な負担をかけることに繋がります。そのため遺言作成時に相続人の調査をしておくことをお勧めいたします。
法定相続情報証明
従来、銀行等にて預貯金の解約・払い戻し手続きを行うには金融機関に戸籍の束を提出することになり、その間は他の銀行に戸籍を提出することができないため、銀行一行ごとに順次手続きを行う必要がありました。平成29年5月から法定相続証明情報制度が開始され、本制度を利用することにより複数の金融機関での払い戻し手続きや、不動産・自動車の名義変更を同時に行うことができます。
手続きの概略は以下のとおりです。
①必要書類(戸籍等)の収集
②法定相続情報一覧図の作成
③申出書を記入し、法務局へ提出
④一覧図の写しの交付
※本制度は遺言作成の段階では利用できません
遺言執行
信頼できる遺言執行者を遺言で指定しておけば、遺言者の意思の実現が確かなもとのなります。また不動産や自動車の名義変更、預貯金の解約といった手続きを円滑に運ぶことができ、相続人の負担軽減にもつながります。